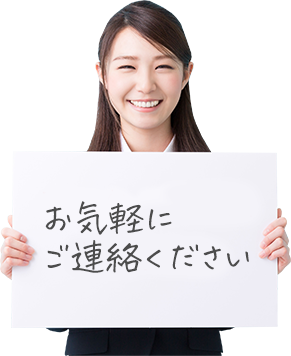顧問社労士の役割とは?契約のメリットと選び方を専門家が解説
はじめに
こんにちは
社会保険労務士法人Fioriです。
企業の労務管理は必要なものですが、皆様の中には以下のようなお悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
- 「従業員の入社・退社の手続きが煩雑で、本業に集中できない…」
- 「毎月の給与計算、本当にこれで合っているのか不安」
- 「法改正があったらしいけど、自社で何をすればいいのか分からない…」
- 「最近、従業員との間で小さなトラブルが増えてきた…」
- 「労務のことで気軽に相談できる相手が社内にいなくて心細い」
企業の成長に「ヒト」の力は不可欠ですが、同時に「ヒト」に関する悩みは尽きないものです。特に、人事労務の専門部署を置くことが難しい中小企業にとって、これらの課題は経営者や担当者の方に重くのしかかります。
そんな時、経営者や人事担当者の力になってくれるのが 「顧問社労士」 です。
この記事では、「顧問社労士」が具体的に何をしてくれるのか、スポット契約との違い、契約するメリット・デメリットから、自社に合った顧問社労士の選び方まで、分かりやすく解説します。
顧問社労士とは何か
顧問社労士とは、継続的な契約を結び、企業の「ヒト」に関する様々な課題解決を総合的にサポートする専門家のことです。
労働社会保険の手続き、給与計算、就業規則の作成、労務トラブルの相談など、人事労務に関する幅広い業務を、専門家の視点から継続的に支援します。単なる手続きの代行屋ではなく、企業の健全な成長を「ヒト」の側面から支える存在です。
顧問社労士の役割と重要性
企業の成長フェーズにおいて、人事労務に関する課題は次々と発生します。例えば、従業員が10名を超えると就業規則の作成・届出義務が生じ、労働時間や安全衛生の管理もより一層重要になります。
顧問社労士は、こうした法的な義務への対応はもちろんのこと、従業員が安心して働ける職場環境づくりや、採用・定着に関するアドバイスまで、企業の状況に応じたサポートを行います。問題が発生してから対処するだけでなく、問題が起こらないようにする「予防」の役割を担うことで、企業が本業に専念できる環境を整える重要な存在です。
顧問社労士契約とスポット契約の違い
社労士との契約には、大きく分けて「顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。
以下の表は、それぞれの違いをまとめたものになります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 契約形態 | 継続的な契約(月額制が一般的) | 都度契約 |
| 特徴 | 日常的な相談、手続き代行、情報提供など包括的にサポート | 特定の業務(例:就業規則の作成のみ)を依頼 |
| イメージ | かかりつけ医(企業の健康状態を常に把握し、予防や早期治療を行う) | 専門外来(特定の症状が出た時だけ受診する) |
スポット契約は特定の課題をピンポイントで解決したい場合に有効ですが、日常的に発生する細かな疑問や、潜在的な労務リスクの発見には顧問契約が適しています。継続的に関わることで、社労士が企業の文化や実情を深く理解し、より的確なアドバイスが可能になります。
顧問社労士が提供する主なサービス
顧問契約の範囲は事務所によって異なりますが、主に以下のようなサービスが提供されます。
給与計算・社会保険手続きの代行
毎月の給与計算は、残業代の計算や社会保険料・税金の控除など、専門知識が求められる複雑な業務です。また、従業員の入社・退社に伴う労働保険・社会保険の手続きは、頻繁に発生する上に提出期限も厳格です。これらの煩雑な手続きを正確かつ迅速に代行し、担当者の負担を大幅に軽減します。
労務相談とトラブル対応
「従業員のパフォーマンスが上がらない」「ハラスメントの相談があった」「問題社員への対応に苦慮している」など、人事労務に関する相談にいつでも応じます。法的な観点だけでなく、他社の事例なども踏まえながら、問題が深刻化する前に具体的な解決策を一緒に考えます。
就業規則の作成と改訂
就業規則は、会社のルールを定め、従業員との無用なトラブルを防ぐためのツールです。法改正に合わせた内容の見直し(メンテナンス)も欠かせません。企業の現状に合わせた就業規則の作成・改訂をサポートし、労務リスクに強い組織づくりを支援します。
顧問社労士を利用するメリット
顧問社労士と契約することで、企業は多くのメリットを得られます。
専門知識を活かした定期的なアドバイス
法改正の最新情報や、他社の動向、活用できる制度など、自社だけでは得にくい専門的な情報が定期的に手に入ります。
法改正への迅速な対応
労働関係の法律は頻繁に改正されます。気づかないうちに法令違反をしていた、というリスクを防ぎ、コンプライアンス(法令遵守)体制を強化できます。
業務の効率化とコスト削減
人事労務の担当者を一人雇用するよりも、顧問社労士にアウトソーシングする方がコストを抑えられる場合があります。また、担当者が手続き業務から解放され、採用や教育といったコア業務に集中できます。
企業に合った助成金の活用提案
国が提供する助成金は、企業の雇用維持や職場環境改善を後押ししてくれる心強い制度です。しかし、種類が多く、要件も複雑なため、自社で最適なものを見つけるのは困難です。顧問社労士は、企業の状況に合わせて活用できる可能性のある助成金を提案し、適切な手続きをサポートします。
顧問社労士を検討すべきケース
以下のような状況にある企業は、顧問社労士の活用を具体的に検討するタイミングと言えるでしょう。
従業員数が10名を超えた、または今後増える見込みがある場合
人事労務の専任担当者がおらず、経営者や他業務の担当者が兼任している場合
従業員の入社・退社が頻繁にある場合
過去に労務トラブルを経験した、または現在トラブルを抱えている場合
法改正への対応に不安を感じている場合
顧問社労士の選び方
顧問社労士は、長く付き合う大切なパートナーです。契約してから後悔しないために、以下の3つのポイントで選びましょう。
-
専門分野や得意な業種の確認
-
社労士にも、就業規則作成が得意、助成金に強い、特定の業種(例:IT、介護、飲食など)の労務管理に精通している、といった専門分野があります。自社の業種や課題に合った強みを持つ社労士を選びましょう。
-
過去の実績や評判の調査
-
事務所のホームページで実績を確認したり、可能であれば契約している企業の評判を調べたりするのも有効です。セミナーなどに参加して、その社労士の考え方や人柄に触れてみるのも良いでしょう。
-
コミュニケーションの取りやすさ(相性)
-
これが最も重要なポイントかもしれません。「ヒト」に関するデリケートな問題を相談する相手だからこそ、話しやすさやレスポンスの速さ、説明の分かりやすさといった相性は非常に大切です。無料相談などを活用し、実際に話してみて「この人になら安心して相談できる」と感じるかどうかを確かめましょう。
顧問社労士との契約の流れ
契約前の準備(問い合わせ・相談):まずは、自社が抱えている課題や悩みを整理し、複数の社労士事務所に問い合わせてみましょう。多くの事務所が無料相談を実施しています。サービス内容や見積もりを比較検討し、最も信頼できると感じた事務所を選びます。
契約後のフォローアップ:契約後は、定期的な訪問やオンラインでのミーティングを設定し、コミュニケーションを密に取ることが成功の鍵です。丸投げにするのではなく、企業の状況を積極的に共有し、社労士をパートナーとして最大限に活用しましょう。
おわりに
顧問社労士は、単なる手続きの代行者ではなく、企業の成長を人事労務の面から支える戦略的パートナーです。
専門家と顧問契約を結ぶことで、経営者や人事担当者の方は煩雑な業務や労務リスクへの不安から解放され、事業の成長という本来の業務に集中することができます。
「まずは自社の課題を相談してみたい」「顧問料がどのくらいかかるのか知りたい」など、少しでもご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案させていただきます。